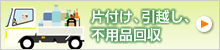![]()
位牌とは、死者の戒名・法名などを記した木の札のことをいいます。中国儒教の死者の霊の依り代が起源とされています。江戸時代に一般化されたと言われており、用途、仕様、形式によりそれぞれ変わってきます。
■ 用途
白木の野位牌…葬儀の時に使用
本位牌(塗位牌、唐木位牌)…四十九日の忌明け後に仏壇に祀られる
寺院位牌…寺院内や寺院位牌堂で用いられる
…など。
■ 仕様
白木位牌、漆を塗り金箔や金粉などで加飾した塗位牌、黒檀や紫檀などで作られた唐
木位牌など。
■ 形式
板位牌…台座に札板が付いた
回出位牌(くりだしいはい)…台座に板が数枚入った箱付
それに関係していくものとして、「永代使用(えいたいしよう)」とは、単に「使用権」と称されることが多いのですが、墓地の一般的な使用権を示す言葉です。ただし「永久」ではなく、「承継者がいるかぎり」期限を定めずに使用を許可されることとなります。
「永代供養墓(えいたいくようぼ)」とは、一般的な「家族単位」で墓の祭祀を行うものではなく、家族の変わりに寺院が責任をもって祭祀する墓のことをいいます。この場合、家族には承継の問題は発生しません。
延命治療とは、治療して回復の見込みがなくなったとしても、死期を延ばすことを目的として行う治療のことをいいます。
この場合、本人の意思よりも、家族や医師の判断で行われることも多く、本人の尊厳を重視した「尊厳死(自然死)」の方が本人にとっては幸せなことではないのかという議論が出ている。ただ、延命治療についての考え方は十人十色なので、そのときの状況において変わってくる。
お清めとは、死穢は伝染すると考えられ、これを払うために通夜や告別式から帰ってきたら玄関に入る前に水で手を洗ったり、塩をまいたりして身体を清めることをいいます。
■ お清めの仕方
(1) 火葬場に行かなかった人にひしゃくで水をかけてもらい、手を洗う
(2) 塩をつまみ、胸・肩にかけてもらう
ただし、最近では死を穢(けが)れとは捕らえない考えもあるので、お清めは不要とする人も多くなってきました。また、浄土真宗ではお清めは行いません。
戒名とは法名とも呼ばれ、仏教に帰依した者に与えられるものであり、仏の弟子としての名前です。檀信徒の場合には、故人の死後に遺族が檀那寺に依頼して、通夜の前に授ることになっています。檀那寺が遠方の場合は葬儀が依頼できないということがあるので、戒名だけは檀那寺に依頼するようにしましょう。
戒名と呼ぶのは、天台宗、真言宗、曹洞宗、臨済宗、浄土宗です。浄土真宗は「法名」、日蓮宗は「法号」と呼んでいます。仏典、経文、俗名の中の一部が戒名に使われます。
神式の場合は、戒名のようなものはありませんが、葬儀では霊じ(仏教の位牌にあたるもの)に「○○○○之霊」「○○○○霊位」「○○○○命(のみこと)」などの霊号が書かれます。
還骨法要とは、火葬後に自宅の後飾り壇に遺骨を安置して行う法要のことをいいます。もともと「還骨」とは、遺骨が自宅に還るという意味から付けられている言葉です。
しかし、最近では斎場やレストラン、ホテルなどで葬儀後の会食に先立って営まれる例が多いようです。
供養とは、お墓や仏壇、寺院などで、故人に供物や花を供え、お経やお線香をたいて、手を合わせることをいいます。元々は「供給資養」からきた言葉とされています。
仏・宝・僧の三宝に供え物をし資養することから、死者の霊に供え物をし死者を養うという意味になりました。供養のために、供花、香典、供物はあり、葬儀や法事を行うことも、供養として行われているものであります。
告別式とは、本来は会葬者全員で葬儀に続いて遺骨を墓地に埋葬する前に行う儀式でしたが、会葬者全員が火葬場まで行くことがなくなった現在では、葬儀での故人との別れの儀式のことをいうようになりました。
告別の方法には焼香、献花、玉串奉奠がああり、最近は、「お別れ会」として行われることがあります。葬儀と告別式はまったく違った意味を持つ儀式なため、葬儀が終わると僧侶はいったん控え室に戻り、あらためて入堂して告別式を行うのが正式の形となっております。
祭祀とは、宗教的概念に基づき,聖職者の指導で行う儀礼的行為とされているが、簡単に言うと、神や祖先を祭ることをいいます。
墓、仏壇、神棚などのことを「祭祀財産」といい、遺産相続の際に控除されるものとなっています。また、祭祀財産を管理したり、葬儀の喪主を務めるなど祭祀を行う人のことを「祭祀主宰者」と呼びます。
死体検案書とは、死亡事由など診察していた医師がいない、あるいは犯罪死・災害死などの異常死など)について警察医(監察医)が死体を検案し発行する証明書のことをいいます。
死亡を証明するためにはは、死亡診断書あるいは死体検案書のいずれかが必要となります。事故死、変死、海外での死亡事故など、少しでも不振な死だと思われることに関しては、警察医の司法解剖が行われ、その際に死体検案書の発行が行われます。
死装束とは、故人の死後、遺体に最後に着せる服のことをいいます。
経帷子を着て、脚には脚絆、手には手甲、足には白足袋に草鞋を履かせ、三途の川の渡し賃と言われる六文銭を入れた頭陀袋をかけ、頭には三角の天冠(三角布)を着けるのが、従来の死装束とされていますが(真宗の門徒はこれを着用しない)、近年は死装束も多様化し、故人の希望や家族の希望で好みの服を着せることも多くなってきました。
自分の死後に着させて欲しいものがあるのであれば、事前に家族に話しておきましょう。
また、死化粧とは、顔の色をいくらかでも生前に近いようにすることをいいます。髪を整え、男性の場合、ひげをそり、女性の場合は薄化粧をします。頬がこけている場合は、含み綿をします。
玉串奉奠とは、仏式の焼香にあたるもので、玉串に自分の心をのせ、神にささげるという意味がこめられているものです。玉串は榊の枝葉を指しています。
■ 玉串奉奠の手順
(1) 祭壇に進んで、神官の前で一礼。
(2) 玉串の枝の根本を右に、枝先を左にして受け取ります。左手で枝の下から捧げるように持つ。
(3) 神官にもう一度礼をし、祭壇前にある玉串案(白木の台)に進む。
(4) 玉串をかるく目の高さまで捧げ、右回りで回転させる。
(5) 根本の方を祭壇に向けて置く。
(6) 正面を向いたまま、少し下がって一礼し、二拍子、一礼をしてから、霊前を下がる。
通夜振る舞いとは、通夜の焼香を終えた人を別室に用意した酒食の席に案内することをいい、通夜に会葬者に飲食を振る舞うことが死者の冥福に貢献すると考えられ振る舞ったことからこの習慣がきたといわれています。
本来は精進料理が出されてきましたが、現在ではあまりこだわらなくなってきました。
納棺とは、枕経が終わった後、遺体を棺に納めることをいいます。この納棺の際には、故人が愛用していた品物や、故人に一緒に持っていって欲しいと思う写真などを入れたりします。
しかし、これらは、火葬のときに一緒に燃やされますので、棺に納める品物については、環境汚染などの問題を考慮して考える必要があるでしょう。
納骨堂とは、簡単にいうと「遺骨をおさめる堂」のことをいいますが、法律的には「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」のことだと称されています。
墓地使用同様に長期預かりもあるので、納骨堂を利用する人々が増加傾向にあるといえるでしょう。
脳死とは、脳の機能が失われたことをもって判定される死のことをいいます。つまり、「脳機能の死」を意味しています。特に生命維持機能を司る”脳幹”の完全な死が脳死と判定される大きな要素となるようです。
植物状態=脳死と考えている人が多いようですが、これはとんでもない間違いです。植物状態の場合は、”脳幹”は機能しているので、自力で呼吸ができ、心臓を動かすことができるのです。
反対に脳死となると自力で生きることができない状態になるので、この違いを覚えておきましょう。
お彼岸とは、川の向こう側を表し、この世に対しあの世を意味しています。
死者を追悼する季節の意味としても使用されれもので、春彼岸は春分の日を中日とする7日間、秋彼岸は秋分の日を中日とする前後7日間を指し、このお彼岸のときにお墓参りをする風習があることはよく知られているはずです。
埋葬とは、お墓に遺体を埋めることをいいます。都道府県によっては土葬も認められていますが、その墓地の規則制限があるので確認しておきましょう。ただし、日本での土葬は全体の1%ほどとなっています。
枕飾りとは、故人の死後、遺体を安置した後に、遺体の側を荘厳(しょうごん)するものです。小机に白い布をかけて、香炉を中央に置き、向かって右に燭台、左側に花立ての三具足を供えます。
枕経とは、死亡直後に遺体を安置した枕元で檀那寺の僧侶がお経をあげることをいいます。
葬式を出す前までは死者は生きている者としての扱いをするべきものなので、あくまで本人に対して読み聞かせるという前提となり、また死後直後の遺族の心をサポートする意味ももっています。
通常は、枕直しをし枕飾りをしたところで行われ、その後に戒名(法名)のこと、葬式の手順など打ち合わせることが一般的となっています。
回し焼香とは、焼香の方式のことで、それぞれの席に香炉を回し、その席で座ったまま焼香する方式です。寺院など畳に座って葬儀を行う場合などに、遺族・親族席では回し焼香をすることもあります。
このほかには、立ち焼香、座り焼香などの方式があります。焼香の仕方には、宗派により多少の違いがありますので、自分の宗派の焼香の仕方を事前に知っておくことも必要でしょう。
民営墓地とは、宗教法人や財団法人などの公益法人が経営する墓地のことをいいます。
民営墓地は事業を目的としているので「事業型墓地」ともいわれています。宗教法人が経営しても、使用者の宗旨を問わないで一般に使用者を求めている墓地もありますので、その場合は、民営墓地に分類されます。
無縁墓地とは、承継者がいなくなってしまったお墓のことをいいます。一般に承継者を失った墓は処分の対象となってしまい、官報に記載され、1年間墓所に立て札を立てて縁者の申告を待たれることになります。
こういった条件のもとで、墓地の管理者は無縁墳墓を撤去することができます。しかしこの場合、遺骨は無縁塔などに合葬されるることとなります。
遺言は、法律的には「いごん」と読まれ、財産分与や葬儀の際の喪主など、死後のことについて書き残すことをいいます。遺言が法律的有効性をもつためには、方式や書式などが民法で詳細に定められているので注意しましょう。
法的効力のある遺言には、自筆証書(全て自書)、秘密証書(自分で作成し、公証人に証明)、公正証書(公証人が作成)があります。ただし、船で遭難したりして死が迫っているときなどは、上記のような遺言はできないので、特別方式遺言が適用されます。
遺言で効力を発揮するのは、財産の処分や分与、子の認知、相続人の廃除、未成年者の後見人の指定、祭祀主宰者の指定など身分に関することとなります。